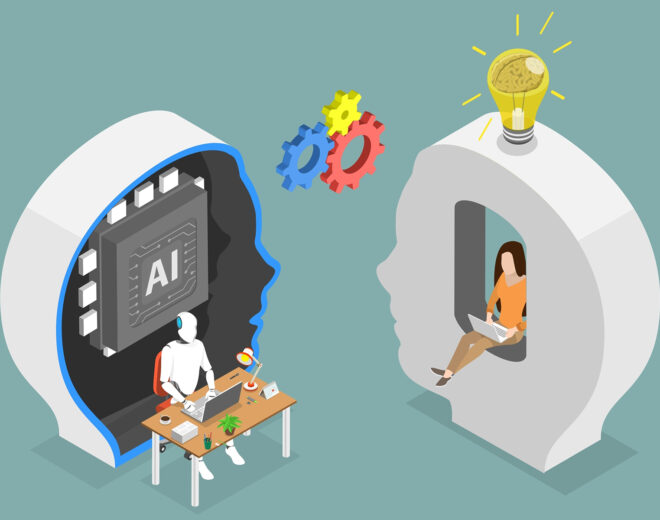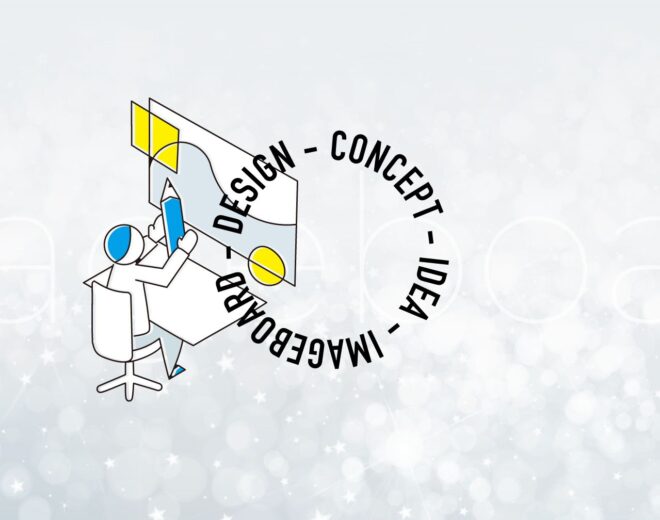PoCで終わらせない、生成AIの「使われる設計」|生成AIとWebの関係#01

こんにちは、代表の丸山です。
Web制作の現場で、日々クライアントと向き合いながらものづくりをしています。
生成AIの進化により、あらゆる業種で業務効率化やアウトプットの高速化が期待される中、私たちのようなWeb制作会社の現場でも、AI活用の動きは確実に広がっています。
企画・設計・ライティング・コーディングにいたるまで、制作プロセスのあらゆるフェーズにAIを取り入れる機会は増えており、その便利さや可能性を強く実感しています。
一方で、こんな疑問もあがっています。
なぜ、生成AIはPoC(概念実証)で終わってしまうことが多いのか?
なぜ、便利だと分かっていても“実際の業務”に根づかないのか?
AIを使う設計と、人が設計する意味はどう変わるのか?
こうした問いをもとに、AIO(AI Optimization)/LLMO(LLM Optimization)の視点から、生成AIとWebの現在地をシリーズとして捉え直してみたいと思います。
これは、ツールの話ではなく「業務をどう再設計するか」という根っこの話。
今回はその第1回、「PoCで終わらせない、生成AIの“使われる設計”」をテーマに、AI導入を“形にする”ために必要な考え方を考察していきます。
なぜ生成AI導入は“止まりやすい”のか?
「生成AIを導入しました」「業務にAIを組み込み始めました」
こうした報告は、いまや珍しくありません。一方で、実際の現場でAIが“定着した”という事例は、まだまだ限られているのが実情です。
これは何も、企業の熱量や予算、スキル不足が原因というわけではありません。もっと根本的な「活用設計の不在」が背景にあるように感じます。
AIを活用しようとするとき、多くの企業はまずPoC(概念実証)を試みます。これは当然の流れですが、そのPoCで「すごい」「便利」と一定の効果を確認した後、実際の業務フローにAIを埋め込む設計に進めず、止まってしまう。ここがひとつの壁ではないかと考えています。
「生成AIを使ってみたが、その後どう業務に取り込んでいいかわからない」「一部のメンバーだけが触っていて、組織全体に広がらない」といった声も多く聞かれます。これは言い換えると、AIを活用する設計ではなく、AIを前提に業務を再設計する視点が欠けているのではないか。
例えば、生成AIをライティング補助として導入したのに、従来通りの承認フローに乗せた結果、かえって工数が増えてしまった──そんな話もありました。
つまり、「AIをどう使うか」よりも、「AIがある前提で、業務をどう組み直すか」が問われているのではないでしょうか。
そうした前提の中で、AIO(AI Optimization)やLLMO(LLM Optimization)という考え方に触れる機会も増えてきました。いずれも、AIをただ使うだけでなく、業務全体をどう組み直すかという視点を含んでいるところに意味があるように感じています。
AIO/LLMOとは?ツールと業務の二重最適化
AIO(AI Optimization)とLLMO(LLM Optimization)という言葉は、ここ最近になって耳にする機会が増えてきました。いずれも生成AIや大規模言語モデル(LLM)を、単なる実験やPoCにとどめず、業務の中に実装していくことを前提とした考え方です。
ただし、AIOやLLMOを特別なフレームワークとして捉える必要はないと思っています。むしろ「ツール活用の最適化(AIO)」と「業務フローの最適化(LLMO)」という、二重の最適化が求められるようになってきた、という自然な流れだと感じます。
例えば、ChatGPTを導入するだけなら、今や誰でも簡単にできます。でも、それを社内のどの業務で使うか、どう活用するか、誰が管理するのかになると、急に難易度が上がります。(AIツールを使って完了する業務と、AIツールを踏まえて“人が判断する”業務の線引きは本当に難しい…)
たとえば、弊社ではWeb広告用のアイデア出しや構成設計にAIを使うこともありますが、配信前の調整や言葉のトーンの見極めは、やはり人の役割として残しています。
つまり、AIOはツールそのものの設計・最適化、LLMOはそのツールを含めた業務全体の再設計というイメージに近いと思います。
私自身、最初はこれらの用語に少し身構えたのですが、実際に社内やクライアントとの会話の中で整理していくと、「ああ、言っていることはとても当たり前のことだな」と感じるようになりました。
| 用語 | 意味 | 対象 |
|---|---|---|
| AIO | AI Optimization(AIの最適化) | ツール・AIそのものの活用設計 |
| LLMO | LLM Optimization(LLMの最適化) | 業務フローや情報設計の再構築 |
デジタル庁ガイドラインに見る業務再設計の必要性
国としても、生成AIの活用には本格的に舵が切られつつあります。
2025年5月、デジタル庁は「生成AIの業務利用ガイドブック(ver.1.1)」を公開しました。これは以前から示されていたver.1.0を更新したもので、より実務的な観点から「生成AIを業務にどう組み込むか」が解説されています。
このガイドブックのなかで、最も印象的だったのは「業務の見直しから始める」ことの重要性が、より明示的に位置づけられた点です。つまり、「ツールを導入して業務を効率化しよう」ではなく、「業務自体を、AIを前提に組み直すことが必要」という視点が明確に示されたということです。
また、ver.1.1ではリスクマネジメントの観点もより詳細になっており、以下のような項目が整理されています。
💬 生成AI利用における主なリスク対策(デジタル庁より)
- ハルシネーション(事実に基づかない出力)への備え
- 個人情報や機密情報の取り扱い
- 著作権やコンテンツの再利用に関する留意
- プロンプトや出力結果の記録・監査
つまり、生成AIの導入は、業務改善だけでなく、ガバナンスやリスク設計とも不可分になってきているということです。
PoCでの技術的評価に留まるのではなく、「組織としてどう使うか」「現場でどう運用するか」までを設計する必要性が、国のガイドラインとしても裏付けられつつあります。
こうした流れを見ると、「AIを導入する=何かに使ってみる」という段階から、「AIがいる前提で、業務の意味や構造自体を問い直す」フェーズに、社会全体がじわじわと移行し始めているのではないか、そんな印象を受けます。
実際、私たちが手がけるWeb制作や運用の現場でも、“AI前提設計”の兆しはすでに始まっています。
Web制作・サイト運用でも“AI前提設計”が始まっている
Web制作やサイト運用の現場でも、「AIをどう使うか」ではなく、「AIがある前提で設計する」意識が、少しずつ芽生え始めています。
たとえば、サイト構成を考えるとき。従来であれば、人間が読みやすいように情報の順番を組み、視線誘導を意識してレイアウトを設計するのが当たり前でした。しかし今では、「AIがコンテンツをどう読み取るか」「APIとしてどう出力するか」など、“人間以外の閲覧者”を前提とした設計が現実味を帯びています。
特に顕著なのが、CMSやFAQ運用の設計における変化です。
たとえば、ある企業では社内に蓄積された問い合わせログをもとに、ChatGPTと連携したFAQの自動生成スクリプトを構築。出力された回答を確認・整備したうえで、社内Botとして実装した結果、月間100件以上の問い合わせが一次対応の段階で自動処理されるようになったそうです。
従来は人手で対応していた部分を「自動応答で解決される領域」と「人の判断が必要な領域」に明確に分けることで、業務全体の流れが再設計されたというこの事例は、まさに“AI前提設計”の好例といえるでしょう。
私たちの制作現場でも、こうした「使われ方を見越してつくる」設計が求められる場面は増えています。とくに、以下のような観点が重要になっています。
- AIに読ませる構造をどう設計するか(構造化・命名規則)
- 出力のために必要な“文脈”や“メタ情報”をどう付与するか
- AIと人がどこで引き継ぐのかというワークフローの設計
これらはいずれも、表面的なUIやトレンドに左右されない、“業務の構造”や“情報の設計”にかかわる話です。
また、Web制作と一口に言っても、目的はさまざまです。ブランド訴求、採用活動、販促、カスタマーサポート…。それぞれの目的ごとに「AIが機能する構造」は異なります。つまり、テンプレート的にAIを埋め込むのではなく、「その業務と組織に合った構造で、AIが動く設計」を都度考える必要があるということです。
このような“前提から設計し直す”という視点は、今後、制作会社の役割そのものを変えていく可能性があると感じています。
まとめ
「生成AIはすごい。でも、業務にはなかなか定着しない。」
そんな声を、クライアントやパートナーとの会話の中で何度も耳にしてきました。その背景にあるのは、AIの性能や導入コストといった話よりも、「私たちの業務そのものが、AIを前提に設計されていない」という根本的な問題なのではないかと感じています。
AIO(AI Optimization)や LLMO(LLM Optimization)という言葉は、少し難しそうにも見えますが、実際はとても現場的な視点です。
「どの業務にAIを取り入れるか」
「誰がそのプロンプトを設計し、結果をどう扱うのか」
「どの業務を“人がやるもの”として残すのか」
そんな問いを、現場の視点で丁寧に設計し直していくこと。そこにこそ、“使われるAI”への入り口があるのだと思います。
Web制作という現場でも、CMSや構造設計、情報の整理など、AIと向き合う場面はこれからさらに増えていきます。だからこそ、ツールを使う前に、「何のために、どう機能させたいか」という設計思想が欠かせないのではないでしょうか。
生成AIの活用がうまくいかないのは、AIが未熟だからではなく、私たちがまだ“活かし方を設計しきれていない”からなのかもしれません。
一度立ち止まって、AI前提で業務を見直してみる。
そのスタートラインとして、本稿が少しでもヒントになれば幸いです。
AIO/LLMO対策のご相談はユニオンネットまで。
AIO/LLMO視点で考える生成AIとWebの関係
#01:PoCで終わらせない、生成AIの「使われる設計」
#02:「誰が言うか」にAIはどう向き合うのか。信頼・ブランドの再定義
#03:「設計されるAI」と「設計する人間」、制作の現場で起きていること
#04:AIは検索を壊すのか?“回遊しないWeb”とLP時代のはじまり
#05:AIO/LLMOを業務に根づかせるには。WebとAIの設計者としての実践知
既存サイトの見直しはもちろん、リニューアルや新規制作に向けた構造設計のご相談も可能です。
この記事を描いたひと

企業のWeb担当者と制作会社の想いをつなげるメディア「untenna」の編集部。