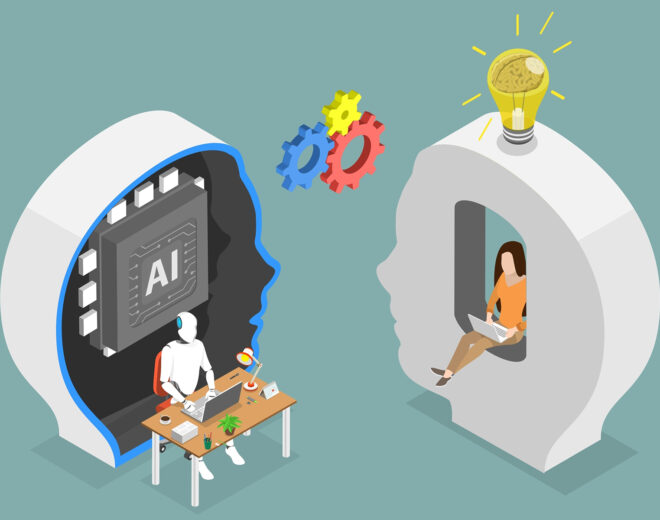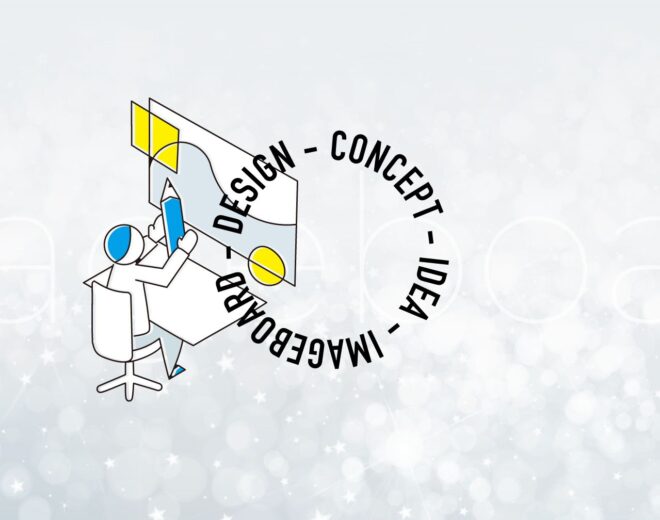「設計されるAI」と「設計する人間」、Web制作の現場で起きていること|生成AIとWebの関係#02

こんにちは、代表の丸山です。
前回は、「PoCで終わらせない、生成AIの“使われる設計”」というテーマで、AIO/LLMOの視点から、「AIをどう使うか」ではなく、「AIがある前提で業務全体をどう組み直すか」が問われているのではないか、AI活用を業務に根づかせるためには“再設計”が不可欠であるという話をしました。
この“前提としてのAI”という視点は、私たち制作の現場でも、日々リアルに感じていることです。
とくに、構造や言語、導線といった「設計そのもの」にAIが入り込んできている。あるいは、AIに引っ張られて設計が変わっていく。そんな局面が確実に増えてきています。
今回はその視点を深掘りし、「設計されるAI」と「設計する人間」のあいだで今、何が起きているのかを整理してみたいと思います。
人がAIを“設計する”プロセス
生成AIの登場以降、「構成を考える」「ライティングを補助する」「ビジュアルを生成する」など、様々な工程でAIを活用するようになりました。
そのとき、ユーザーである私たちが求められるのは、「何を、どのように伝えると、意図に近いアウトプットが返ってくるか」という設計力です。これはAIを“使う”のではなく、“設計する”という行為に近い。
たとえば、以下のようなプロセスは、私たちの制作現場でも日常的に発生しています。
| 活用シーン | 設計の工夫ポイント |
|---|---|
| 構成案の作成 | 読者像・目的・トーン・制約条件を記述 |
| ビジュアル生成 | 光の向き・構図・色味・使用媒体を明記 |
| 再プロンプト設計 | 出力に対する評価 → 改善指示を具体的に反映 |
このように、AIを活かすには「設計」が不可欠。そして設計力とは、いかに自分の頭の中のあいまいなイメージを論理的に伝え、意図した成果物を引き出すかという、極めて人間的な知的作業です。
一見、AIが代替しているようで、実は「人間の設計力」が以前にも増して問われている。それが、いま起きている変化の本質のひとつだと感じています。
AIに“設計される”人間
一方で、私たち人間がAIによって“設計されている”場面も確実に増えています。
たとえば、SEO施策におけるコンテンツ制作の場面では、AIが検索上位の記事構造やキーワード配置を分析し、「こうすれば上がる」という“正解”を提示するサービスが増えてきました。
また、Adobe FireflyやCanvaといったツールでは、ユーザーのラフな入力に対して、一定のルールに基づいた配色やレイアウトをAIが提案してくれます。一見ありがたい仕組みに見えますが、これは逆に言えば、「美的バランスはAIが握っている」という状態でもあるわけです。
この図式になったとき、私たちはAIに設計される側に回っていると言えるのではないでしょうか。
もちろん、これはネガティブな意味ではなく、私たちがどこまでをAIに任せ、どこからを人が担うのかという線引きを意識できているかどうか。
「AIに任せていいこと/任せすぎないこと」を判断する視点こそ、いま最も必要とされている“設計力”なのかもしれません。
| 領域 | AIによる“設計”例 | 設計者としての人間の視点 |
|---|---|---|
| コンテンツ構成 | 検索上位記事の分析に基づく自動構成提案 | 本当に伝えたい順番か?自社の文脈と一致しているか? |
| デザイン | テンプレートから自動配色・レイアウト | ブランドカラーやトーンに合っているか? |
| コピー | キーワード最適化に基づく文体提案 | 自社らしい語り口か?顧客の言葉として自然か? |
“人の手が通る”設計に宿るもの
では、AIが設計にも関わり、成果物の大部分をサポートしてくれるようになった今、「人が手を加える意味」とはどこにあるのでしょうか?
私自身、AIを使ってアイデアを出したり、記事構成をつくる補助として活用することは多々あります。ただ、最終的に採用されるのは、“整いすぎていない案”であることがほとんどです。
✨ “整っていない”からこそ惹かれるポイント
- コピーとビジュアルのズレが「引っかかり」を生む
- 空間の余白が“意図しないリズム”を生み出す
- テキストの言い回しが人間っぽく印象に残る
といったような、“正解ではないけれど魅力的な何か”は、今のところAIではつくりにくい。つまり、「ちょっとズレてる」が持つ力を、人間は本能的に知っているということだと思います。
さらに、Web制作では“感情の設計”も重要です。
- クライアントの話し方からにじむ熱量
- フィードバックのニュアンスから伝わる価値観
- 曖昧な指示の行間を読んで設計に反映する力
こうした、人と人のやりとりから生まれる情報を設計に織り込むことは、今も人間にしかできない仕事です。
AIによる設計が進むからこそ、「整わなさ」や「曖昧さ」まで設計に取り込める人間の価値が、より明確になる。そんな時代になってきていると感じます。
まとめ
今回は、「設計されるAI」と「設計する人間」の視点から、制作の現場で起きている変化についてお話ししました。
生成AIが業務に浸透する中で、私たちは「どう使うか」だけでなく、「どう使われているか」という視点も持ち始めています。プロンプト設計や構造設計といった領域では、AIを設計する立場にある一方で、AIによって導かれた構成やレイアウトに、人間が寄せていく場面も増えています。
そんななかで、整いすぎないデザインや、会話の行間からにじむ感情のやりとり、言葉にしきれない違和感を丁寧に拾うこと。そうした“人にしかできない設計”の価値は、むしろ以前よりも高まっているように思います。
AIO/LLMOのような技術的な視点が注目される今だからこそ、私たち人間が担うべき“設計の意味”を問い直すことが求められているのではないでしょうか。
AIO/LLMO対策のご相談はユニオンネットまで。
AIO/LLMO視点で考える生成AIとWebの関係
#01:PoCで終わらせない、生成AIの「使われる設計」
#02:「誰が言うか」にAIはどう向き合うのか。信頼・ブランドの再定義
#03:「設計されるAI」と「設計する人間」、制作の現場で起きていること
#04:AIは検索を壊すのか?“回遊しないWeb”とLP時代のはじまり
#05:AIO/LLMOを業務に根づかせるには。WebとAIの“設計者”としてできること
既存サイトの見直しはもちろん、リニューアルや新規制作に向けた構造設計のご相談も可能です。
この記事を描いたひと

企業のWeb担当者と制作会社の想いをつなげるメディア「untenna」の編集部。