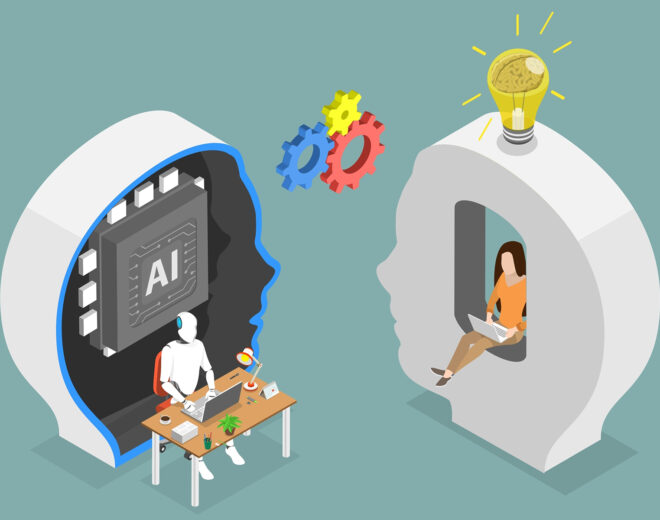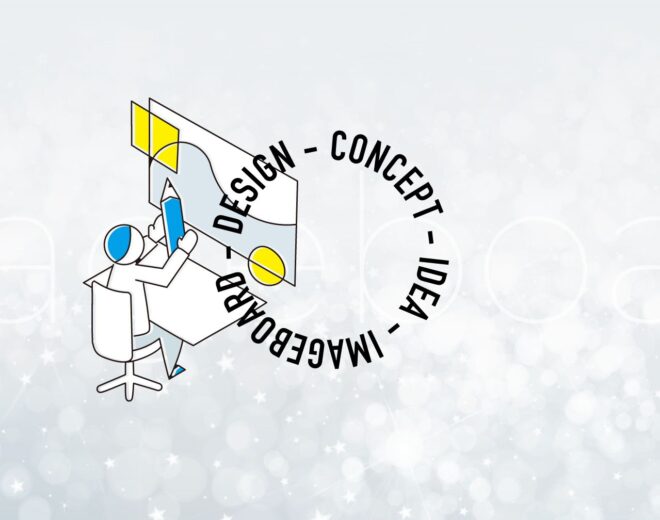「誰が言うか」にAIはどう向き合うのか。信頼・ブランドの再定義|生成AIとWebの関係#03

こんにちは、代表の丸山です。
第1回では「PoCで終わらせない、生成AIの“使われる設計”」、第2回では「設計されるAIと設計する人間」をテーマに、制作の現場で起きているAIとの関わり方の変化をお伝えしました。
今回は、もう少し本質的なテーマとして、「信頼」や「ブランド」といった“誰が言うか”の価値がAI時代にどう変わるのかを考えてみたいと思います。
「情報」は溢れても、「誰が言ったか」は重みを増す
ChatGPTのような生成AIによって、文章・アイデア・提案のアウトプットは一気に手軽になりました。誰でも数秒で、ある程度“それらしい”テキストが生成できます。
しかしその一方で、こんな感覚も広がっています。
- 「誰が書いたかわからない文章」は、読まれない
- 「中の人が見えない情報」は、信じられない
- 「その人だから聞きたい」コンテンツだけが残る
つまり、「情報の質」よりも「誰が言っているか」という“発信の主体”が、これまで以上に問われるようになってきているのです。
これは、生成AIによる大量生産が可能になったからこそ起きている逆転現象だと言えるでしょう。文章や情報は無限に出せる。でも、その“背景にある人や企業の想い”に価値が集まり直している。
発信の信頼性は“継続性”と“関係性”で決まる
では、どうすればAI時代に信頼される発信ができるのか。私が感じているのは、以下の2つの視点です。
1. 継続性のある発信が信頼をつくる
信頼されるメディアや企業の多くは、「発信が続いている」ことが共通しています。
定期的に、ぶれない軸で情報を届けていること自体が、その姿勢や価値観の表明になっている。
これはたとえAIを活用していたとしても、「人が責任を持って見届けている」ことが伝われば、十分に信頼の対象になり得ます。中身の正しさだけでなく、“続けてきた重み”がブランドを支えているのです。
| 継続性 | 定期的な発信が“実在”と“想い”を伝える |
| 一貫性 | コンテンツ間のトーン・文脈・方向性が統一されている |
| 関係性 | 具体的な“誰に向けた発信か”が明確 |
| 透明性 | どのようにAIを活用しているかが示されている |
| 文脈の設計 | 投稿の目的、受け手との関係性が明示されている |
② 誰かとの“関係性”の中にある言葉が残る
また、信頼される発信は「語りかける相手」が明確です。
それは顧客かもしれないし、採用候補者や地域の人かもしれません。
誰に向けて、どんな関係性の中で語っているのか。そうした“人間関係の文脈”がある発信ほど、心に残るものです。AIが生成したとしても、その文脈を人が設計していれば、ちゃんと人の言葉として届きます。
ブランドは「言葉の一貫性」と「体験の重なり」でできていく
企業やサービスの“ブランド”とは何か。それは単なるロゴやビジュアルではなく、「あの会社の言うことなら信じられる」「このサービスはこういう想いで作られている」といった“言葉の一貫性”と“体験の重なり”です。
たとえばWebサイトのコンテンツひとつ取っても、
- 採用ページで語られている価値観と、ブログの言葉が一致している
- 商品紹介のトーンが、SNSでの投稿と違和感なくつながっている
- 代表メッセージが、実際の社内文化と一致している
こうした“ズレのなさ”が、ユーザーにとっての「信頼」につながっていきます。
AIはこうした一貫性の維持にとても役立ちます。言葉のトーンや使われているキーワードを揃える、過去の発言との整合性を保つ、といったことはAIが得意とする領域です。
だからこそ、「AIで発信できる」ことを前提にしたうえで、「発信の根っこにある想いは何か」「その言葉が誰に向けられているのか」を設計する必要があるのです。
AIによる発信と、ブランドの“身体性”の分岐点
ここでひとつの課題も見えてきます。
AIが生成した文章やコンテンツは、たしかに便利で、それっぽくはあります。ただ、そこに“語り手の身体性”がないと、いくら正しくても「届かない」と感じる場面があるのです。
たとえば、次のようなケース
- 代表あいさつの文章に、その人らしさが滲んでいない
- 採用メッセージに、現場のリアルな声が含まれていない
- 製品紹介が、競合と同じような言葉にしか見えない
こうした状況を防ぐために必要なのが、「その会社/人ならではの表現」を掘り起こし、AIにも引き継げるように設計することです。
💡 AIに引き継げる“その人らしさ”の要素
- よく使う語尾や接続語(例:「〜と思います」「〜ですね」)
- 独自の表現スタイル(例:「数字で語る」「比喩を多用する」など)
- ストーリーテリングの流れ(自己開示→課題提起→提案 など)
- 禁則ワード/使わないトーンの指定(例:「〜しなければならない」は避ける)
これらを整理しておくことで、AIが発信する際にも、“その人らしさ”をまとったアウトプットが可能になります。
Web制作に求められるのは、“AIと人の境界設計”
Web制作の現場でも、こうした「AIと人の境界設計」が求められるようになっています。
| 領域 | AIが担う部分 | 人が担う部分 |
|---|---|---|
| Webサイト文章 | 下書き生成、トーン合わせ | 意図や背景の追加、最終調整 |
| SNS発信 | アイデア出し、原稿草案 | 投稿タイミングの判断、リプライ対応 |
| お問い合わせ対応 | 一次対応(定型Q&A、FAQ) | 特殊対応や提案、関係性の構築 |
| 採用コンテンツ | キャッチコピー、社員紹介の要素抽出 | 現場のリアルな声、写真選定、構成設計など |
こうした役割分担を明確にすることで、AIと人の強みを活かした“信頼される情報設計”が可能になります。
そして、Webサイトというメディアが担うのは、こうした「AIでも人でもない、企業としての言葉」の設計です。
- 企業として、どんな言葉で語りかけるか
- どこまでが自動で、どこからが手動か
- その線引きに一貫性があるか
AIO/LLMOの視点でいえば、これは“言葉の構造最適化”であり、“ブランド体験の再設計”でもあります。
まとめ
今回は、“誰が言うか”の価値が再定義されつつある時代において、生成AIとどう向き合うかを考えてみました。
AIによって情報発信の手段は広がりましたが、だからこそ「その言葉に、誰の想いが宿っているのか」がより強く問われています。そしてその答えは、単なるプロフィール情報ではなく、「どんな言葉を使い」「どんな関係性の中で語られているか」にあります。
Webサイトも、SNSも、パンフレットも、「何を言うか」ではなく「誰が、誰に向けて、どう言うか」の設計がより大切になってきている。AIはその設計を補助してくれる頼もしいパートナーですが、ブランドを体現する“語り手”は、やはり人です。
AIO/LLMOという考え方が普及する中で、こうした“人の意図をどう組み込むか”という設計視点こそが、今後の制作や発信に求められていくのではないでしょうか。
AIO/LLMO対策のご相談はユニオンネットまで。
AIO/LLMO視点で考える生成AIとWebの関係
#01:PoCで終わらせない、生成AIの「使われる設計」
#02:「誰が言うか」にAIはどう向き合うのか。信頼・ブランドの再定義
#03:「設計されるAI」と「設計する人間」、制作の現場で起きていること
#04:AIは検索を壊すのか?“回遊しないWeb”とLP時代のはじまり
#05:AIO/LLMOを業務に根づかせるには。WebとAIの“設計者”としてできること
既存サイトの見直しはもちろん、リニューアルや新規制作に向けた構造設計のご相談も可能です。
この記事を描いたひと

企業のWeb担当者と制作会社の想いをつなげるメディア「untenna」の編集部。