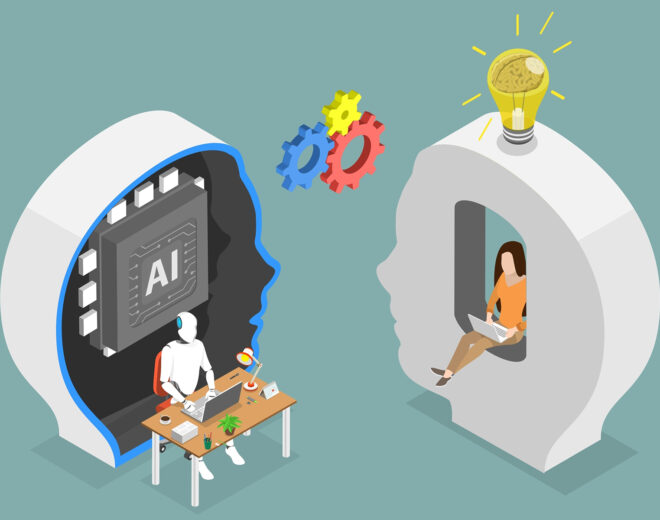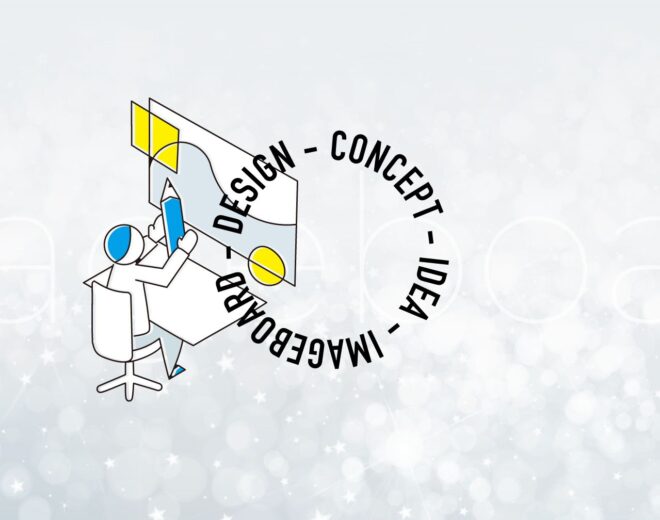AIO/LLMOを業務に根づかせるには。WebとAIの設計者としての実践知|生成AIとWebの関係#05

これまで4回にわたり、「生成AIとWebの関係」をAIO(AI Optimization)/LLMO(LLM Optimization)の視点から読み解いてきました。
第1回では、PoCで終わらせない“使われる設計”の必要性
第2回では、「設計されるAI」と「設計する人間」の交差点
第3回では、「誰が言うか」がブランドになる時代への変化
第4回では、「回遊しないWeb」とLP時代のはじまり
そして今回は最終回として、「AIO/LLMOをどう業務に根づかせるか」という本質的な問いに向き合いながら、Web制作会社としてのスタンスを言語化してみたいと思います。
AIO/LLMOは“導入”ではなく“設計”の話
多くの企業では、生成AIを「新しいツールの導入」として捉えがちです。もちろん間違いではありませんが、それだけでは“使いこなす”には至らないのが実情です。
実際、成果を出している企業は、AIを前提に「業務そのものをどう設計し直すか」という視点で取り組んでいます。
ここで、AIOとLLMOの違いを整理してみましょう。
| AIO(AI Optimization) | LLMO(LLM Optimization) | |
|---|---|---|
| 対象 | ツール導入・利用最適化 | 業務構造や情報設計の最適化 |
| 主な課題 | 精度や効率の向上 | 意図通りの運用・再利用可能性 |
| アプローチ | マニュアル・ナレッジ整備 | ワークフローと構造の再構築 |
| 必要な視点 | ツール理解とチューニング | 文脈編集・構造言語化能力 |
AIOは“ツール”の話であり、LLMOは“構造”の話。両者を分けて考えるのではなく、業務全体を2階層で捉えるような視座が求められます。
事例紹介|「AI前提」で業務を見直すということ
実際の企業では、ChatGPTなど生成AIを活用してFAQの自動生成・運用を行い、業務フローそのものを設計し直す取り組みが進んでいます。
1. 江崎グリコ × Alli(Allganize)
課題
年間13,000件以上の社内問い合わせが発生。人力対応に限界があり、対応スピードとナレッジ整備に課題。
再設計の流れ
① よくある質問をFAQとして整理・構造化
② AIチャットボット「Alli」を導入し一次回答を自動化
③ 回答ログをもとにFAQを随時更新し、AI精度を継続的に向上
成果・設計ポイント
- 問い合わせ件数を30%削減
- 担当者のFAQ更新負荷も大幅軽減
- AIO的にはAIツール導入+活用フロー最適化
- LLMO的にはFAQ構造整備と改善PDCAの実装
参照元:
【Glicoグループ様】30%の社内問い合わせ対応を削減。顕在化したバックオフィスの課題を「Alli」で解決llganize公式ブログ|江崎グリコ導入事例
2. アジアクエスト × 情シスQ&A Bot
課題
社内のSlackで定型的なIT系問い合わせが頻発。担当者の工数が膨らみ、対応品質もばらつきがあった。
再設計の流れ
① 過去の問い合わせログをもとにナレッジを整理
② SlackとChatGPTを連携し、Botが自動回答
③ 回答候補を人が補完・改善し、ナレッジ
④ UI・UXも含めた全社展開
成果・設計ポイント
- ユーザー満足度の高いBot応答を実現
- 業務工数の圧縮+ログ活用による改善サイクル確立
- AIO:Slack×ChatGPT連携による自動化支援
- LLMO:人の判断・修正を含む運用設計とナレッジ管理
3. LIFULL × keelai
課題
社内71%が生成AIを利用する環境の中で、属人的な運用から脱却し、業務設計に沿ったAI活用を目指した。
再設計の流れ
① 社内問い合わせをSlackで統一管理
② ChatGPT APIと連携したkeelaiで回答を生成
③ Function Calling を使って各種処理を自動化
④ GitHub Actions などと連携し、ナレッジを展開
成果・設計ポイント
- 半年で20,700時間以上の業務時間を創出
- 月間利用者511名、社内浸透に成功
- AIO:Slack連携+API駆動の自動化
- LLMO:ナレッジを活用した業務構造の再設計
参照元:
LIFULL、生成AIの社内活用により半年間で 20,000時間以上の業務時間を創出| 株式会社LIFULL(ライフル)
Webサイトは“AIに伝える”ための最小単位になる
Webサイトもまた、変化の波の中にあります。これまでは「人に見せる情報の場」だったWebが、今では「AIに正確に伝えるための情報実装単位」としての役割を強めています。
以下のような構造化データは、検索エンジンやAIアシスタントに意味を伝える鍵です。
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Organization",
"name": "株式会社ユニオンネット",
"url": "https://www.unionnet.jp",
"logo": "https://www.unionnet.jp/logo.png",
"sameAs": [
"https://x.com/unionnet_inc",
"https://www.instagram.com/unionnet.days/"
],
"contactPoint": {
"@type": "ContactPoint",
"telephone": "+81-6-6941-2388",
"contactType": "customer support",
"availableLanguage": ["Japanese"]
}
}
</script>このような実装を含め、今後のWebサイトには以下のような要件が求められていきます。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 構造化 | JSON-LDやFAQ schemaなどのマークアップ対応 |
| 意味づけ | コンテンツごとの用途や対象を明確化 |
| 再利用性 | 広告・SNS・検索結果に展開しやすい構造 |
つまり、Webは“人とAIの両方に伝える”ための設計が必要になるのです。
“作って終わり”から“運用まで設計する”へ。
AIと人の翻訳者でありたい。
生成AIを導入する際、しばしば「ツールを導入する=活用している」という誤解が生まれがちです。しかし実際には、AI導入はスタートに過ぎず、業務に根づかせ、成果に結びつけるには“運用までを見据えた設計”が不可欠です。
社内ナレッジの共有に生成AIを活用する場合、ChatGPT APIと連携したFAQ自動応答の仕組みを導入したとしても、それが継続的に機能するには、
- どの問い合わせをAIに渡すか
- どのタイミングで人が介在するか
- どうやってナレッジを更新・改善していくか といった情報の構造化と業務の流れを横断的に設計する視点が求められます。
このような設計を支えるうえで、私たちユニオンネットが大切にしているのは、“AIと人の翻訳者”としての立ち位置です。
現場では、クライアントが抱える課題が抽象的であることが多く、「何に困っているのか」「どの情報が必要なのか」を言語化するところから始まります。それをAIが理解しやすい形式に変換し、また、AIの出力結果を人が使いやすい情報へと再編集して届ける。この“意味の橋渡し”こそ、私たちの価値だと考えています。
さらに、こうした翻訳力は単体のプロンプトやUI設計にとどまらず、
- コンテンツの構造設計(例:メタ情報、タグ設計、FAQカテゴリ分け)
- CMSやマークアップでの構造化
- 運用フェーズを見越した業務フロー設計 といった「業務 × 情報 × AI」の全体設計にも関わります。
つまり、ツールを導入するだけでなく、運用し続けられる“しくみ”を設計し、実装後もともに改善していく存在。それが、私たちが目指す制作会社の姿です。
ユニオンネットでは、AIO/LLMOの支援において、以下のようなスタンスで伴走しています。
| ユニオンネットが大切にしていること |
|---|
| ツール選定や導入よりも、業務と情報の設計から支援すること |
| 人とAIの役割分担を明確にし、判断ポイントを設計に落とし込むこと |
| コンテンツ設計だけでなく、CMSやマークアップを含む構造化まで対応すること |
| 実装後の保守・改善を見据え、チームで回せる運用の仕組みを考えること |
“意味を持たせる設計”は、まだまだ人間の仕事です。
情報の設計を担う者として、AIと人が共に働く環境を“仕組み”で支える。それが、これからの制作会社に求められる役割だと考えています。AIが進化しても、「どう伝えるか」を設計できるのは人間です。だからこそ、私たちはその力を磨き続けたいと思います。
AIO/LLMO対策のご相談はユニオンネットまで。
AIO/LLMO視点で考える生成AIとWebの関係
#01:PoCで終わらせない、生成AIの「使われる設計」
#02:「誰が言うか」にAIはどう向き合うのか。信頼・ブランドの再定義
#03:「設計されるAI」と「設計する人間」、制作の現場で起きていること
#04:AIは検索を壊すのか?“回遊しないWeb”とLP時代のはじまり
#05:AIO/LLMOを業務に根づかせるには。WebとAIの設計者としての実践知
既存サイトの見直しはもちろん、リニューアルや新規制作に向けた構造設計のご相談も可能です。
この記事を描いたひと

企業のWeb担当者と制作会社の想いをつなげるメディア「untenna」の編集部。