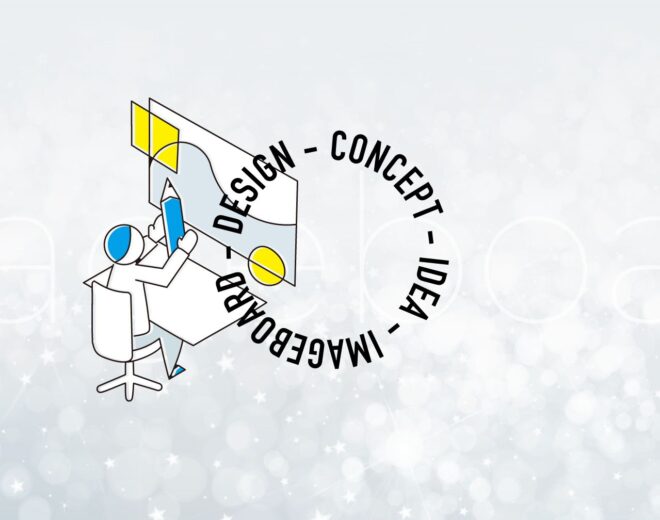AIは検索を壊すのか?“回遊しないWeb”とLP時代のはじまり|生成AIとWebの関係#04
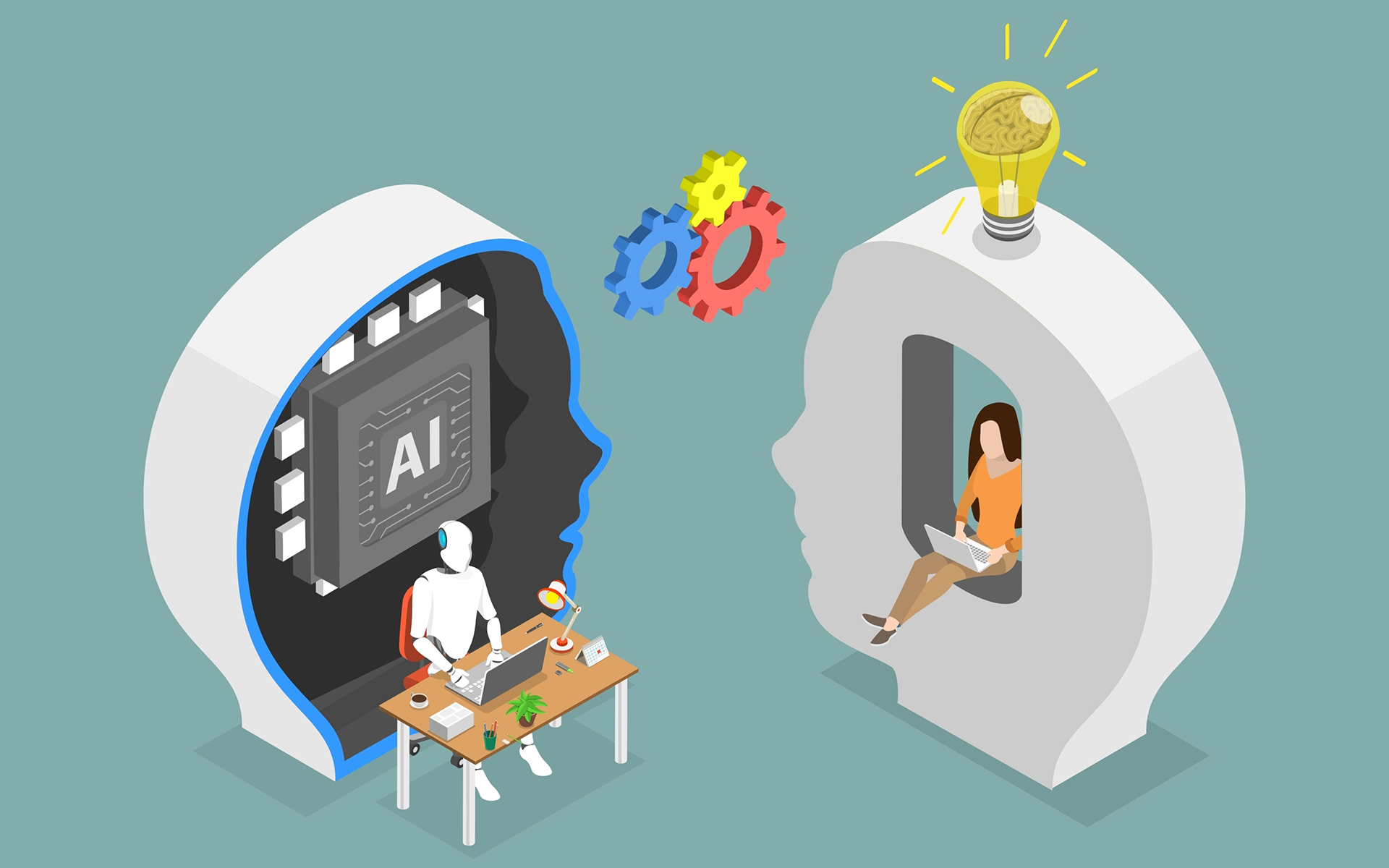
こんにちは、ユニオンネットの丸山です。
前回は、「設計されるAI」と「設計する人間」の視点から、AIとクリエイティブの関係を掘り下げました。今回は、検索体験とWebサイトのあり方に焦点をあてます。
私たちはこれまで、“探して見つけてもらう”ことを前提にWebサイトを設計してきました。しかし、生成AIの台頭はこの構造そのものに揺さぶりをかけています。
果たして、AIは検索を壊すのか?
そして、これからのWebは何を目指せばいいのか?
本稿では、「回遊しないWeb」と「LP時代」の到来という視点から、制作現場で起きている変化を見ていきます。
1. SEOは“構造の最適化ゲーム”へと再定義された
これまで、SEOは「人が検索すること」を前提とした施策でした。タイトルにキーワードを含める、メタディスクリプションを調整する、構成を論理的に整理する……といった細やかな工夫は、検索結果での上位表示を目指すためのものでした。
しかし、今やSEO施策の多くはAIでも支援できるようになっています。
- 競合記事の構成を自動抽出し、最適な見出し構成を提示
- ページごとの内部リンク構造を分析し、改修プランを提案
- 想定検索意図に基づいてFAQや見出し案を生成
こうした最適化支援ツールの進化により、SEOは“調整”から“最適解ゲーム”へと変化しています。AIが膨大なパターンを高速に試し、“一番効く”構成を提示してくれる。その意味で、人間が担ってきた調整業務は、徐々にAIに置き換えられつつあります。
Googleが目指していたのは、“検索のない世界”
実はGoogle自身も、こうした未来を想定して動いてきたことがわかります。
たとえば、検索結果に表示されるリッチリザルトや構造化データの活用。これは、ユーザーがサイトに遷移する前に「答えを提示する」ための施策でした。
また、ナレッジパネルやゼロクリック検索と呼ばれるような動きも、「検索した瞬間に答えがある」世界を目指すものでした。情報の“発見”よりも“提供”に重きを置く設計にシフトしていたのです。
生成AIによる検索支援(SGE:Search Generative Experience)もその延長線上にあります。検索バーの代わりに“AIとの対話”で答えを得る、という未来をGoogleは見据えているのです。
つまり、Googleは検索の“入口”ではなく、“答えの出口”を担おうとしている。
この流れを読み解くと、Webサイトの役割もまた変わっていかざるを得ないと気づかされます。
Webサイトの役割は「回遊」から「吐き出し」へ
これまで私たちは、「ユーザーが複数ページを回遊しながら情報を得る」ことを前提にサイトを構成してきました。トップページからカテゴリページへ、さらに詳細ページへ──こうした“動線”を設計することが、UI/UX設計の基本でした。
しかし、生成AIがユーザーに要約された情報を直接届けるようになれば、ユーザーが“サイト内を回遊する”という体験は減っていきます。その結果、Webサイトに求められる役割は変化します。
私たちが従来行ってきたのは、ユーザーがサイト内を「回遊」する前提の設計でした。
トップページ
├─ サービス一覧
│ └─ 各サービス詳細ページ
└─ 会社情報・採用・お問い合わせ
このような階層構造と導線設計によって、「ユーザーを導く」体験を重視してきたのです。しかし、生成AIはそうした回遊プロセスをすっ飛ばします。
User → AI(検索意図)→ 直接コンテンツへジャンプ
この変化を受けて、私たちは「構造の見せ方」ではなく、「意味の抽出しやすさ」を重視したWeb設計を考える必要が出てきます。
LPは“AI時代のフォーマット”になり得る
この流れと連動するように、今、再びLP(ランディングページ)設計が注目を集めています。
LPは、特定の目的やキーワードに対して、「答えを一枚で伝える」ことを重視した構成です。回遊を前提とせず、「情報の到達点」として設計される点で、まさに生成AI時代にフィットする存在と言えます。
たとえば、
- 採用情報専用のLP
- サービス内容をまとめた1ページ構成
- 商品やキャンペーンの訴求ページ
これらは、構造化・文脈化がしやすく、生成AIにも認識されやすいフォーマットです。
<section id="service-overview">
<h2>サービス概要</h2>
<p>私たちは〇〇業界に特化した〜</p>
</section>
<section id="features">
<h2>選ばれる理由</h2>
<ul>
<li>豊富な実績</li>
<li>スピード対応</li>
<li>明瞭な価格設定</li>
</ul>
</section>
<section id="cta">
<h2>お問い合わせ</h2>
<a href="/contact">こちらからご相談ください</a>
</section>セクションの意味が明確にマークアップされていれば、AIが情報を収集・要約しやすくなります。また、ユーザーにとっても「とりあえずこのページを見れば全体像がつかめる」という安心感があり、離脱率の低下やCV率の向上にもつながる傾向があります。
つまり、回遊させるのではなく、「ここに着地させる」Web設計が本流になりつつあるのです。
Webは“入口”から“意味の出口”へと進化する
このように、検索とWebサイトの関係性が変わっていく中で、Webサイトの役割も「入口」から「意味の出口」へと変化していきます。
重要なのは、単に情報を並べるのではなく、「ユーザーのために意味を整理し、AIのために意味を構造化する」ことです。
| 従来の目的 | これからの目的(AIO的) |
|---|---|
| 情報を読ませ、回遊を促す | 情報を要約し、抽出されやすくする |
| サイト内の導線を整理する | 意図と関係性を明示する |
| 見た目やUIで魅せる | 意味と文脈で伝える |
たとえば、
- FAQやサポート情報をAIが読みやすい形で整理する
- 採用情報を求職者の目線に合わせて意味づける
- サービス説明をそのまま広告やSNSに展開できる構造にする
といった具合に、“意味の構造化”が重要になります。
Webサイトは、もはや「読まれるもの」ではなく、「抽出されるもの」へ。AIの入力として最適化されたWebを設計できるかどうかが、新しい競争軸になっていくのではないでしょうか。
6. 制作会社が担う“着地型の意味設計”
最後に、こうした変化の中でWeb制作会社に求められる役割を整理します。
これからのWeb制作は、
- 回遊させる設計ではなく、“着地させる”設計
- 見せ方の装飾ではなく、“意味の提示”
- ページ間の導線設計ではなく、“1ページ完結の価値提示”
へとシフトしていきます。
その中でWeb制作者は、以下のような問いを引き受けていく必要があります。
- このページは誰にとって、どんな答えを出しているのか?
- どの部分をAIが拾い、どう要約されると望ましいか?
- 人が読む/AIが抽出する、その両立はできているか?
UI設計者ではなく、“意味の設計者”としてのWeb制作者へ。
これこそが、AIO/LLMO時代における私たちの新しいスタンスではないでしょうか。
まとめ
検索が“終わりの体験”になる時代に、Webは“情報の出口”として再設計される必要があります。
その中で見えてきた変化は次の3つです。
- SEOはAIによる構造最適化ゲームへ
- LPはAI時代の標準フォーマットに
- Webは意味の出口として再定義される
私たちWeb制作会社にできることは、「人とAIの両方に意味が届く構造」をつくること。そして、検索や回遊ではなく、「着地」に価値を置いたWeb設計を磨いていくことです。
次回は、シリーズ最終回として「AIO/LLMOを業務に根づかせるには」というテーマから、Web制作会社としてどんなスタンスが求められるかを掘り下げてみたいと思います。
AIO/LLMO対策のご相談はユニオンネットまで。
AIO/LLMO視点で考える生成AIとWebの関係
#01:PoCで終わらせない、生成AIの「使われる設計」
#02:「誰が言うか」にAIはどう向き合うのか。信頼・ブランドの再定義
#03:「設計されるAI」と「設計する人間」、制作の現場で起きていること
#04:AIは検索を壊すのか?“回遊しないWeb”とLP時代のはじまり
#05:AIO/LLMOを業務に根づかせるには。WebとAIの“設計者”としてできること
既存サイトの見直しはもちろん、リニューアルや新規制作に向けた構造設計のご相談も可能です。
この記事を描いたひと

企業のWeb担当者と制作会社の想いをつなげるメディア「untenna」の編集部。