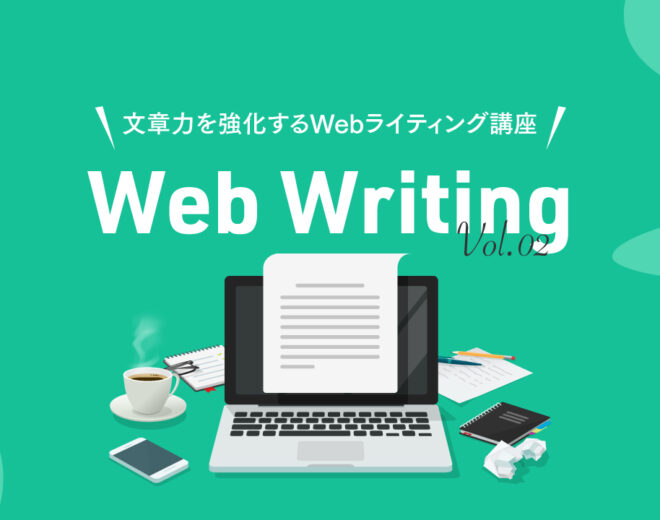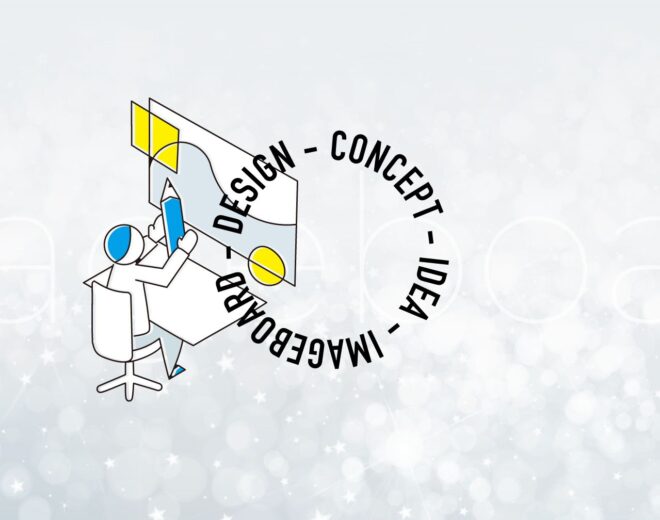【Web担当者必見】コーポレートサイトでのブログの正しい書き方。

多くの企業は自社のコーポレートサイトを持っている昨今ですが、コーポレートサイト内のブログページを活用しきれていない企業も多いのではないでしょうか。
ホームページなどのコーポレートサイトは検索上位表示が難しく、SEO対策を取るという役割を考えてもブログ機能をしっかりと活用していく必要があります。
そこで本記事では、コーポレートサイトのブログページでは何を書けばいいのかと悩む企業のWeb担当者に向けて、「コーポレートサイトのブログの書き方」について詳しく解説していきます。
本記事を参考にブログページを充実させ、SEOのみならずユーザーからも高い評価を受けられるコーポレートサイトに仕上げてみてはいかがでしょうか。
企業がコーポレートサイトでブログを運営する理由
企業がコーポレートサイトでブログを運営する一番の理由は、直接的にお仕事に繋がるという点にあります。
企業のコーポレートサイト内で質の高いブログを執筆、公開することでサイトに訪れたユーザーがブログを閲覧、その結果価値を見出してもらい、お仕事に繋がる、または商品の購入に繋がることを目的としています。
基本的に企業は、自発的に企業や顧客にアプローチをかける営業方法、いわゆるプッシュ型の営業スタイルが基本となります。
しかし、コーポレートサイト内のブログでしっかりと価値提供が出来れば企業や顧客の目に留まり、関心も持ってもらえるため営業せずとも商品・サービスが売れる、いわゆるプル型にシフトすることが可能です。
顧客の獲得難易度は非常に高いとされていますが、コーポレートサイト内のブログにて価値提供をすることで顧客側からアクションを起こしてくれるため、多くの企業がサイト内ブログの執筆を始めたという流れです。これが、企業がコーポレートサイトでブログを運営する理由です。
企業にとってのブログの役割とは
大前提として、企業のコーポレートサイト内ブログは、どのような役割を担っているのでしょうか?実は、前述のような価値提供の後の成約だけでは留まらず、非常に多くの役割をになっています。
コーポレートサイト内ブログをスタッフが更新することによって顧客に親近感を与える、自社がどのような業務を行っているのかを認知してもらうなど、企業のコーポレートサイト内ブログの役割は多岐に渡ります。
そんな役割の中でも、大きな割合を占めるのが「企業の利益に貢献する」という役割。企業ブログが利益に貢献する役割の例は以下の通り。
- アクセスを集めるブログ記事を公開
- SNSのシェアなどで情報拡散
- ユーザーが共感できる記事更新で信頼感を獲得
- 第3者による2次、3次の情報拡散
- ファン化したユーザーに行動喚起
- 商品を購入してもらい顧客へ
企業のコーポレートサイト内ブログは、これらの役割を全て果たします。
つまり、この役割を把握できていない状態でのブログ運営・記事作成は、思うようなアクセスを得られないばかりか、最終的な目的である「企業利益への貢献」も期待できなくなってしまいます。
コーポレートサイトのブログの書き方7つのポイント

ここからは、コーポレートサイト内ブログの書き方を7つのポイントにまとめて解説します。ブログなんて書いたことがない、という方も多いかと思いますが、ポイントさえ理解出来ていれば問題なくブログを執筆することは可能です。
ここで紹介するポイントをしっかりと取り入れて、ブログの執筆に取り組んでみてください。7つのポイントは以下の通り。
- 読者が興味を持つ内容を選ぶ
- 思わずクリックしてしまうタイトルを付ける
- ブログの冒頭(リード)で読者の共感を得る
- 企業ブログの記事の構成を組み立てる
- 企業ブログ記事に
- ブログ記事を読み終わったあとで行動喚起
- ブログ記事の品質をチェックする
1つずつ詳しく解説してきます。
1. 読者が興味を持つトピックを選ぶ
まずブログを書く際のポイントとして、読者が興味を持つ内容の記事を執筆するようにしましょう。例えば、Web制作会社のブログ記事なのにブログの内容は建設関連のものなどであれば読者は興味を持てません。
ブログ記事を書く前に、まずはどのような内容のテーマであればサイトに訪れてくれた読者が興味を持ってくれるのか。ここを明確にする作業から取り組んでいく必要があります。
また、読者に興味のない内容の記事を書くことで、読者の離脱率が上がります。読者の離脱率が高まることでSEOからの評価も下がってしまうため、記事を書く際には読者が興味を持ち、最後まで読んでもらえるようなブログ記事に仕上げるよう心掛けましょう。
2. 思わずクリックしてしまうタイトルを付ける
コーポレートサイト内のみならず、ブログ記事を投稿すると検索エンジンにも反映され、特定のキーワードで検索した際に検索結果上に表示されるようになります。
そこで重要になってくるのが、思わずクリックしてしまうタイトル付けです。読者は、何かしらの悩みを解決するために検索します、。そこで、似たようなタイトルの記事がたくさん並びますが、思わずクリックしたくなるようなタイトルを見つけたら、それをクリックします。
記事を読まれるためには、必ずタイトルが見られるのでクリックされるような興味を惹くタイトルを付けるテクニックが必要になってきます。これは、コピーライティングという文章のテクニックで、読者の興味を惹く方法としては非常に有効とされています。
3. ブログの冒頭(リード)で読者の共感を得る
タイトルをクリックされてブログが表示された際、一番初めに出るファーストビューはブログの冒頭部分、リードと呼ばれる部分となります。このリード部分は初めて読まれる文章となるため、ここで読者の心をグッと惹きつけるとその先も読み進めてもらえます。
リード文では、「このようなお悩みありませんか?」のような、読者の悩みを筆者側で代弁してあげる形式が無難かつ効果的な手法となっています。読者の悩みを代弁することで、「これ自分のことだ!」と思わせ、その先を読んでもらうためにも、共感を生ませるようなリード文を考えてみましょう。
4. ブログの記事構成を組み立てる
ブログはある程度長文となるため、最初から最後まで読んでもらえる可能性は高くありません。そこで、最後まで読んでもらうための施策として、記事の構成を組み立てていく必要があります。
コーポレートサイト内に掲載するブログは、価値提供のためのノウハウ記事となるため、執筆を担当するスタッフの感情をそのまま載せたような文章を読者は望んでいません。
そのような感情的で誰も求めていないようなブログにしないためにも、まずはブログ記事内に盛り込みたい要素を箇条書きで書き出し、見出しとしておくことでブログで伝えたい内容の軸がブレることがなくなります。
ブログを書いてはいるけど、自分の書きたいことばかり書いてしまう、という方は、箇条書きからの見出し構成を試してみてはいかがでしょうか。
5. ブログ記事をより伝わる内容に補強する
ブログ記事が完成したら、そのまま投稿するのではなく、より伝わる内容に補強することをおすすめします。ブログは書いていくうちに自分だけが理解出来る内容に陥りがちです。
頑張って書いて投稿した結果、肝心の読者が読んだ際にあまり伝わらないような記事に仕上がってしまうことは珍しくありません。そこで誰が読んでも伝わる、理解度が深まる内容に仕上げるために補強する必要があります。
ブログ記事の内容を補強する際のポイントは以下の通り。
- 細かな説明や補足を入れる
- 文字ばかりになる場合は画像を挿入する
- 公式の見解を書きつつ、自分の意見も述べる
- 自分の意見を書く際は、根拠がある情報かを明確にしておく
- 他の記事から情報を探してきた際は引用元のリンクを記載する
上記のポイントを踏まえて、書き終えたブログを見返すと出来ていない部分があると思うので、その箇所をしっかりと補強していきましょう。この作業があるだけで、読者の理解度がグッと高まり、コーポレートサイト自体の評価も上がります。
6. ブログ記事を読み終わったあとで行動喚起
ブログを最後まで読んでいただいた読者の方は、読了感だけでは満足しません。ここで必要になってくるのが、行動指標です。前述の通り、読者がサイト内のブログ記事を読んでいるということは何かしらの悩みを解決したいから。
ブログで悩みを解決した読者ですが、実はこれだけでは満足してくれません。読者のほとんどは、悩みを解決した後に、背中を押してもらえることを望んでいるんです。
つまり、ブログの巻末、まとめ部分で行動喚起(CTA)をアナウンスしてあげることでやるべきことが明確になり、悩むことなく問題解決へ一直線で走り出します。
この行動喚起をしないと、情報だけをインプットした状態で行動に移してくれず、結果としてただ読んだだけの状態になってしまいます。
ブログのまとめ部分には、必ず問題解決に繋がる手段をアナウンスしてあげましょう。
7. ブログ記事の品質をチェックする
いよいよブログが完成しました。ここまででも中々大変な作業でしたが、ブログは慣れの部分が大きいので毎日のようにブログ記事を執筆していると自然と身に付いてくるので継続することが一番の成長に繋がります。
ここで、ブログが完成したからといってすぐに投稿するのは少し待ちましょう。せっかくのブログ、読者に満足してもらえるものに仕上げたいですよね。
なので、投稿の前に今一度、ブログ記事の品質をチェックしてみましょう。
SEO対策を意識したブログの書き方

コーポレートサイトのブログの書き方について詳しく解説しましたが、ここからはSEO対策を意識したブログの書き方についても理解しておきましょう。
検索上位に表示されると新規ユーザーが自然と流入してくれるため、集客のために広告を打ち出したり営業に力を注ぐ必要がなくなってきます。
せっかく検索エンジンに認識させるのであればSEO対策も行い、検索上位表示を狙ったほうが効率良く集客出来るので、ここで解説するポイントを意識しつつブログの執筆に取り組んでみてください。
キーワード選定
検索上位表示を狙うためには、キーワード選定が必須となってきます。キーワード選定とは、特定のキーワードで検索された際に検索の上位を狙えるようなキーワードを選定するリサーチ作業のことを指します。
例えば、Googleなどの検索エンジンで「Web制作」と検索すると大量にサイトが出てきます。このキーワードで検索の1位を獲得しようとしても、1企業のブログでは到底1位の記事には適いません。
しかし、「Web制作 大阪」のように2つのキーワードを組み合わせることで検索結果はグッと絞られます。このように、需要はあるものの競合が多すぎないキーワードを見つける作業をキーワード選定と言います。
このキーワード選定で穴場のキーワードを見つけ、検索上位に自社のブログが表示されるようになれば検索からの自然流入は大幅に増え、新規顧客が自動的に増えてきます。
ブログ記事を執筆する際は、穴場のキーワードを選定する作業から取り組んでみましょう。
同業他社との差別化
コーポレートサイト内でブログ記事を掲載していく行為は、確実にユーザー満足度の向上やSEOからの評価に繋がります。しかし、このような施策を打っているのは自社だけとは限りません。
同業他社も同様の施策を打っている場合、オンライン上でも競い合うことになるため、そこでも同業他社より優位に経つ必要があります。
ここで打つべき施策は、同業他社との差別化を図ることです。書こうとしていたキーワードの記事を、同業他社がすでに執筆していた場合、凡庸な内容を書いても勝てる見込みは薄いです。
このような場合に効果的な施策が同業他社との差別化です。すでに同業他社が執筆している記事を確認したうえで、その記事よりも専門性を高くしたり、情報量を多くするなど、どこか1つでも勝てる要素を作ることで同業他社を出し抜くことが可能になります。
SEOに最適であろう文字数を理解する
SEOは、ユーザーの満足度を重点的にチェックしています。つまり、ユーザー満足度を高めることでSEOからの評価も上がり、検索上位表示を狙えるという仕組みになっています。
そこで関係してくるのが、ブログ内の文字数です。
基本的にSEOで上位表示を狙う場合、文字数が多い方が情報が濃いと判断される傾向にありますが、それは検索されるキーワードによって変動します。
例えば、「PC 強制終了」というキーワードであれば、PCの強制終了の方法だけを知りたいユーザーが検索します。つまり、「PC 強制終了」のブログ記事が3万文字あり、一番最後に強制終了のコマンドを書いているような記事であれば、ユーザーの満足度は確実に下がります。
簡潔に知りたいであろうキーワードは短めに、しっかりと詳しく解説するようなキーワードであれば内容も濃く長めの文章で解説するなど、キーワードの検索意図を理解した上でブログの文字数を定めるようにしましょう。
同じような内容の記事を作らない
自社のコーポレートサイト内でブログ記事を書いていくうちに、内容が似ている記事が仕上がることがあります。しかし、このような記事は作らないようにしましょう。
同ドメイン内に、内容が重複している記事が存在すると、各記事がSEO評価を分散してしまい、せっかく検索上位に表示出来ていた記事も順位が下落してしまう可能性があります。
同じような内容の記事は必ず1つにするよう、定期的にブログ内の記事を確認しておきましょう。
コーポレートサイトに掲載するブログの正しい書き方!のまとめ
本記事では、コーポレートサイトに掲載するブログの書き方について詳しく解説しました。書き慣れないうちは毎日1記事なんて相当ハードな業務となりますが、慣れてさえしまえば午前中に1本書き上げられるようになったりもします。
ブログは慣れの要素が多いので、まずはたくさん書いてWebライティングに慣れるところから始めていきましょう。また、書き方についても細かく解説しましたが、基本的なポイントとなるので書いていくうちに自然と出来るようになってきます。
SEO対策に関しても、感覚で馴染んでくることも多いので、まずはたくさん書くことから始めてみましょう。その結果、営業や広告などを一切行わずに検索エンジンからの自然流入だけで事業を回せるなんてことも実現可能です。
本記事を参考に、自社のコーポレートサイトへブログ記事を掲載してみてはいかがでしょうか。
習慣にするのが一番むずかしいよね、実際。

この記事を描いたひと

企業のWeb担当者と制作会社の想いをつなげるメディア「untenna」の編集部。